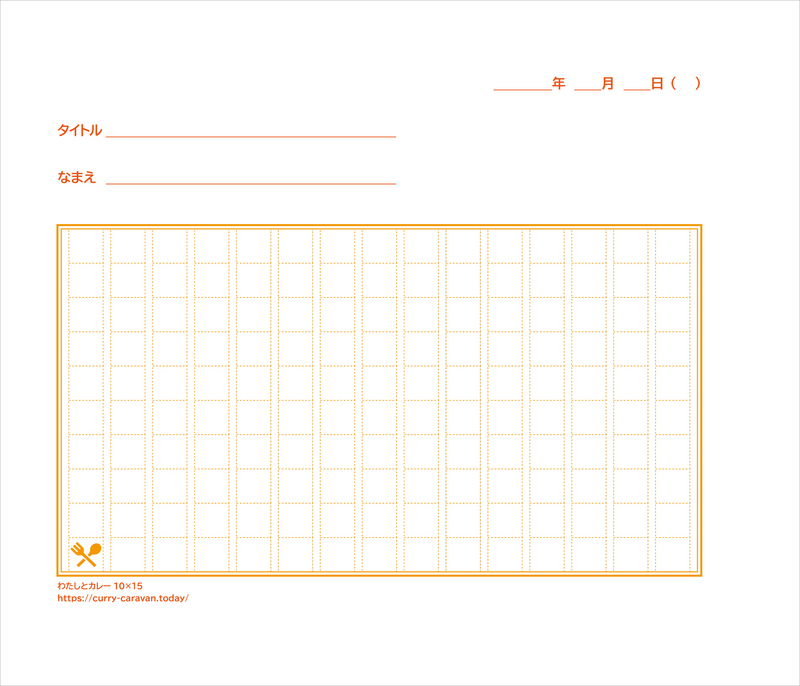3回つくったので、ふり返ってみた。
10年前に出版した『つながるカレー:コミュニケーションを「味わう」場所をつくる』(フィルムアート社, 2014)は、どうやら在庫がなくなったようだ。スパイスと調理器材とともに全国のまちを巡って、そのとき・その場の流れに身をまかせて、出かけた先の食材でカレーをつくる。「ひととであい まちでつくる 旅するカレー」(「カレーキャラバン」のコンセプト)…ぼくの日常生活のなかで、そんな旅がくり返されていた。
「カレーキャラバン」は、2019年の秋を最後に、無期限の活動休止となった。COVID-19の影響で、この4年近くは身動きが取れず、結局のところは(いろいろな事情があって)、以前のような活動には戻れなくなった。
そして、今年の4月から「カリーキャラバン」の活動を開始した。「カレー」と「カリー」。紛らわしくて申し訳ないのだが、いま書いたとおり、「カレーキャラバン」は無期休業である。バンドでいえば、解散はせずにソロ活動に入るというやつで、「カレーキャラバン」の精神は引き継ぎつつ、(似ているけどちがう)「カリーキャラバン」なのである。
今年の春から夏にかけて、4回、「カリーキャラバン」として活動した。墨田区(東京都)にオープンした「オラ・ネウボーノ」で3回、美波町(徳島県)で1回。少しずつだが、日常生活のなかに、またスパイスが戻ってきた。 「オラ・ネウボーノ」は、あたらしいタイプのシェアキッチンで、「グランドレベル」(田中元子さん+大西正紀さん)が手がけた場所だ、あの「喫茶ランドリー」から徒歩圏にある。この場所の面白さについては、ぼくではなく、主宰者である大西さんが(たぶん)書いているはずだ。ぼくが惹かれたのは、「まちのフードコート」というフレーズで、シェアキッチンでありながら、偶然の出会いがありそうな設えに見えたところだ。「カレーキャラバン」のときのように、通りがかりの人と一緒につくることはできないかもしれないが、誰が来るのか(そもそも来るのかどうか)わからないところがいい。もちろん設備は整っているし、なにより5月にオープンしたばかりなので、すべてがピカピカだ。直感的に、ここでカレーをつくってみたいと思った。
しばらく前に「ゆるさがあれば(8)」で書いたように(7年近く前の記事)、「オラ・ネウボーノ」は、当然のことながらきちんとしている。なにより、カウンターがあるので、「つくる人」と「食べる人」は物理的に隔てられる。だからこそ、その気になるともいえる。腕に自信のある人、いずれは店を持とうという人は、シェアキッチンで現場の感覚をつかむことができる。じぶんや親しい仲間うちだけで試作をくり返すのではなく、リアルな「食べる人」の反応を知ることができる。味を「世に問う」という意味では、シビアな実験の場所になる。
路上でつくるときには、通りすがりの人が手伝ってくれたり、不意の差し入れがあったり、いくつものハプニングがあった。「カレーキャラバン」では、毎回、その予期せぬ出来事を期待しながら旅を続けていた。だから、整えられたシェアキッチンは、だいぶちがう環境だ。施設を利用するわけだから、利用時間(営業時間)は、あらかじめ決まっている。キッチンはフロアの奥まったところにあるので、行きずりの人とは出会いにくい。むしろ、ちゃんと看板を提げて、気づいてもらう必要がある。シェアキッチンでカレーをつくるときには、いろいろと工夫が必要だ。
それでも、(ぼくにとって)「オラ・ネウボーノ」が魅力的なのは、フードコートのような設えだ。一つのフロアに、3つのキッチンがあって、同時に複数の人が利用することになる。だから、ぼくが奥のキッチンでカレーをつくっていると、横にはスイーツの店があり、入り口の近くにはコーヒーの店がある。そんな光景になる。その組み合わせは毎回変わるので、じつに楽しい。

写真:2024年6月15日(土)オラ・ネウボーノにて
5月19日(日)、6月15日(土)、7月20日(土)と、月に1回のペースで「オラ・ネウボーノ」でカレーをつくってみた。3回つくってみて、いろいろと気づくことがあった。(たとえば、ソロ活動をどのように展開するかについては、別の機会にくわしく書きたい。)
他の利用者は(おそらく、ぼくだけを除いて)、商売である。つまり、料理でもお菓子でもコーヒーでも、値段がついている。「カリーキャラバン」のカレーは、無料である。タイミングさえ合えば、タダでカレーを食べることができる。
タダのカレーはあるのか
「キャラバン」を名乗るからには、旅に出かけなくては、と思っている。5月の末には美波町(徳島県)でカレーをつくったが、最近は、もっぱら「オラ・ネウボーノ」で、月に一度のペースで活動を続けている。たんにカレーをつくるだけでなく、カレーをつくりながら、コミュニケーションや場づくりについて考えている。その意味で、シェアキッチンは、手を動かしながら思索にふけるための実験室のようなものだ。
「タダのランチはない」という言い回しがある。日本語だと「タダより高いものはない」というやつだ。うまい(美味い)話には注意しよう(きっと何か「裏」がある)という教訓をふくんでいる。*1
「タダのランチはない」という話は、もともとは、アメリカの酒場の「販売戦略」からきているという。ビールとともにランチがタダで配られるのだが、塩分が多くなっていて(ハムとかチーズとか)、客は、ランチを食べながらビールをたくさん注文してしまう。結局のところは、お金をたくさん使うという仕組みになっているのだ。
「カレーキャラバン」では、無料でカレーを配っていた。そのことにどのような意味があるのか、何のためにそんなことをしているのか、出先でたびたび聞かれることがあった。もちろん、「タダのカレー」に怪しさを隠せない人にもたくさん出会った。そんな道楽のようなことをしているから、たいしたカレーをつくることができないのだと、叱られたこともある。値段をつけてきちんと稼ぐつもりでカレーつくらないと、味を極めることはできないだろうという、極めて真っ当な意見だった。
『つながるカレー』にも書いたが、あるとき、自腹でカレーをつくってタダで配っていることについて、「楽しいなら続ければいい」と、背中を押された。オトナなら、趣味にお金をつぎ込むことはあるし、飲み会に参加したことを考えれば、ひと晩で5000円程度は(ためらいなく)使っているはずだ。当時、3人のメンバーで活動していて、毎回、一人がだいたい5000円を負担するかたちで「タダのカレー」を実現させていた。なるほど、月に1回くらい、自腹を切って趣味の活動を楽しんでいるのなら、わざわざ理由を考えなくてもいいのだ。たまたま、ゴルフや釣りではなく、路上でカレーをつくってタダで配っているというだけだ。
 写真:2024年6月15日(土)オラ・ネウボーノにて
写真:2024年6月15日(土)オラ・ネウボーノにて
そんな声に激励されつつ、『つながるカレー』のなかでは、「ビジネスモデル」に対比させながら、ぼくたちの活動を「赤字モデル」ということばで語った。それは、一杯のカレーへの対価が、金銭的なやりとりではなく、知り合いができたり、楽しい会話があったりという交換・交歓によってもたらされるいう考えにもとづくものだ。金銭的には「赤字」だが、それに見合う「何か」をえていると考える。それが「赤字モデル」だ。
だが、いまあらためて考えてみると、「赤字」ということばを使うこと自体、金銭的な交換、等価交換をふまえて発想しているということだ。「売らなくていい」「売れなくてもいい」という姿勢は、よくよく考えると「ビジネス」として成り立たないことへの「後ろめたさ」のようなものが表れているようにも思える。おそらく、「赤字モデル」ということばではないのだ。黒字と赤字を両極とする軸を大きく転回させるか、あるいは別の軸をくわえて理解するということなのではないだろうか。
どうやらぼくは、10年分の「カレーキャラバン」の思い出にしばられていたようだ。どこかで、「あのころ」に戻りたいという想いがあったのかもしれないが、そんなことは不可能だ。皮肉なことに、そのことは、COVID-19が教えてくれた。
これからは、「カリーキャラバン」をとおして、あたらしい旅のしかた(場づくりの方法や態度)をつくってゆくのだ。「カリーキャラバン」の活動をとおして、「赤字モデル」に代わる、あたらしい理解を創造してみようと思う。
*1:もちろん、(ランチそのものには)値段がついていなくても、さまざまなコストがかかっているという示唆でもある。