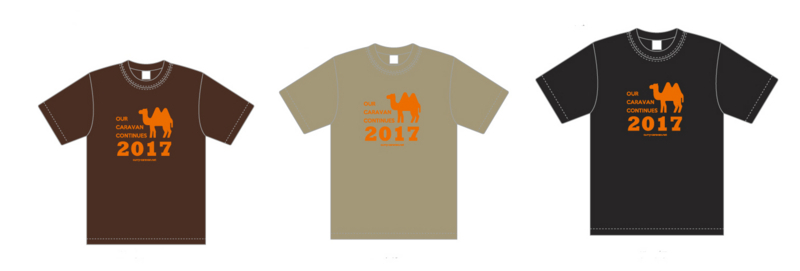芋煮に学ぶ
秋の訪れとともに動きが活発になり、こんどは、山形に出かけることになった。秋の山形といえば、芋煮である。今回は、まさにそのタイミングに合わせて、企画されたのだ。サードシーズン4回目(通算67回目)。山形の芋煮については、これまでに、いろいろな記事を読んだことがある。巨大な鍋をクレーンでかき混ぜるという場面は、たびたびニュースの映像などでも見かけるものだ。『玄米せんせいの弁当箱』という漫画のなかには、芋煮のレシピをめぐる「バトル」のようすが描かれている。いろいろと盛り上がっていることは多少なりとも知っていたものの、その現場に行くのは初めてだ。
今回は、おもに五十嵐さん(2月に盛岡で実施したカレーキャラバンで知り合った)とやりとりしながら準備をすすめた。どうやら敬老の日あたりが「解禁」の合図となって、そのあと、外にいても寒くない程度の頃合いまでが、芋煮のシーズンらしい。実際には、2か月足らずだろうか。シーズン中は、河川敷などで芋煮を楽しむのだという。今回は、その芋煮の集まりに紛れてカレーをつくるという趣向だ。
場所の候補となったのは、馬見ヶ崎川の河川敷。これまでに、全国のあちこちを巡りながら、60数回の旅を続けてきたが、河川敷でカレーをつくったことはなかった。残念ながら、河川敷についてはあまり好ましいイメージを持てずにいた。山奥に出かけて渓流のそばでキャンプをするならともかく、街なかの河川敷から思い浮かぶのは、あれこれと「禁止」する立て看板だ。まずなにより、そもそも河川敷で火を使うことは禁じられていることが多い。川が行政区域の境界になっている場合には、川の「こちら」と「あちら」で決まり事がちがっていることもある。たとえばバーベキューのシーズンになると、あっという間にゴミで汚れてしまう。酔って騒いで、界隈に暮らす住民からは苦情が出る。河川敷だけではない。近所のコンビニのゴミ箱までもが、宴の残骸であふれる。
その結果として、「バーベキューのための場所」が整備されることもある。決められた区画で、いくつものルールに従いながらバーベキューがおこなわれる。のびやかなはずの「外」での活動が制限され、形式ばったものになってしまう。だから、「河川敷でやりましょう」と言われたときには、なんとなく窮屈そうなイメージしか頭に浮かんでこなかったのだ。
ぼくたちは、前日の晩に、買い出しをしておくことにした。地元のスーパーに行くと、店内には「芋煮コーナー」があった。里芋はもちろん、ネギ、こんにゃくなどがすぐそばに置かれていて、うどんやカレーのルー(どうやら「シメ」にカレーを入れるやり方もあるらしい)、ビールやおつまみの類いまで並べてある。必要なものは、この「コーナー」でひととおり揃うようだ。ぼくたちは、あくまでもカレーキャラバンなので、カレーのための食材を買った(もちろん、そのなかに里芋はふくまれているが)。
なにより驚いたのは、そのスーパーの駐車場の傍らにも「芋煮コーナー」があったことだ。店内は食材だが、こっちは芋煮用器財の貸し出しだ。ラックの上には、鍋や基本的な調理器具、さらにはゴザまで置かれている。これらの器財が無料で貸し出されているのだ。しかも、借りるのにいちいち名前や連絡先を書くような手続きはない(ように見えた)。そもそも、「見張り」の人がいないのだ。すぐに「見張り」のことを考えたり、返却されるのかどうか心配したりすること自体が、ぼくの了見のせまさというか、想像力の乏しさなのかもしれない。
借りたら返すのはあたりまえだ。つぎに使う人のことを考えるなら、きれいに洗っておこうと思う。芋煮への愛があればこそだ。食材も調理器具も、気軽に調達できるようになっている。スーパーに行っただけでも、芋煮への想いの強さが伝わってくる。ぼくたちは、一つひとつに驚いて声をあげたり写真を撮ったりしていたが、山形の人びとにとっては、ごく「あたりまえ」なことなのだろう。いちいち騒いだりしないはずだ。

直火の威力
そして、翌朝。予報どおり、雨が降っていた。じつは前日に「場所取り」のつもりで橋の下の一角に貼り紙をしておいた。橋の下なら、雨でもなんとかなるからだ。河川敷に向かっている途中で、五十嵐さんから連絡があった。すでに、ぼくたちの貼り紙の前にブルーシートが広げられているとのこと。メッセージとともに送られてきた写真を見ると、かなりの大所帯のようだ。貼り紙の効力はさほどなかったようだが、大きなブルーシートのご一行のすぐそばにテントを張って、カレーをつくればいい。そう思いながら到着し、クルマから荷物を下ろした。
厚い雲が空をおおっているものの、雨が上がったので、なんとかなるだろうという想いで、橋の下ではなく空の下に場所をつくることにした(大所帯のグループのすぐ近くだと、やりづらい感じもした)。また降りはじめるかもしれないが、空の下は、やはり開放感がある。ぼくたちは、水場のそばにテントを張った。河川敷は、驚くほどきれいだった。ゴミは落ちていない。騒々しく、あれこれと「禁止」を告げる立て看板も見当たらない。
先ほど書いたような、河川敷のイメージはことごとく塗り替えられることになった。河川敷には、コンクリートの丸い台がところどろに敷設されている。決して大げさな話ではなく、文字どおり芋煮のための「舞台装置」だ。七輪(炭火)やガスバーナーなどではなく、直火で鍋を炊くのだ。


すぐ隣りの「舞台」では、五十嵐さんの友人たちが、芋煮の準備をはじめていた。河原からいくつか大きめの石を拾ってきて、かまどをつくって鍋をのせる。そして、薪に火をつける。コンクリートが敷かれているのは、そのためだ。鍋を火にかけるやり方としては、一番「正統」なのではないだろうか。つまりこの河川敷は、芋煮用に整備されているのだ。薪は勢いよく燃えはじめ、鍋から湯気が立ち上った。なんだか、カセットコンロを使っているのが恥ずかしいような気分にさえなる。
そして水道は、もちろん水栓がついている。ぼくたちが、街なかの公園で出会った「あの水道」ではない(くわしくは「ゆるさがあれば(5)」を参照)。コンクリートの「舞台」があるくらいなので、もちろん水は自由に使える。そういえば、昨日のスーパーでは、食材のみならず薪やゴミ袋までもが入った「セット」販売のチラシもあった。ことごとく、まちは「芋煮フレンドリー」なのだ。それは、すばらしい「ゆるさ」だと理解することもできる。一人ひとりが、芋煮を愉しみたい。その「自由」への想いが束ねられると、モノを揃えたり、貸し借りしたり、ゴミを拾ったり、一連のふるまいまでもが整えられて、持続可能なかたちに研がれてゆく。きちんとしているからこそ、「ゆるさ」を保つことができる。というより、「ゆるさ」を守るためには、(きちんとすべきところを)きちんとしなければ、あっという間に無秩序へと向かうのだ。ゴミだらけの河川敷になってしまうということだ。
「外」で愉しむことのできる時期がかぎられているからだろうか。もちろん、里芋の旬の時季もある。一年のうちの大切な「シーズン」のために、準備も片づけも怠らない。「禁止事項」を定めれば、それを守ること(そして守られなかったときにペナルティーを科すこと)を考えがちになる。結局のところは、じぶんたちで決めた「禁止事項」にしばられて、どんどん窮屈になる。「ルール」という考えそのものを、あっけらかんと乗り越えて、芋煮は、もはや「文化」となって、まちにとけ込んでいるのだろう。
そして、この芋煮の「文化」を支えているひとつの原動力は、レシピの多様性にあるのかもしれない。山形に暮らす知人は、ふだん芋煮をつくるときには、何種類か用意するらしい。職場には、出身地のちがう同僚がいるからだという。どこまで気を遣うかはともかく、いくつもの味つけ(レシピ)を尊重する。その上で、芋煮の「正しさ」や「正統性」について語らう。SNSでは「#芋煮戦争」というハッシュタグさえあるほどで、レシピをめぐる「バトル」は続いてゆくにちがいない。だが、シーズンがくるたびに、「正しさ」について語るからこそ、コミュニケーションは絶えることがないのだ。そもそも「火種」がなければ、鍋は熱くならない。

「イモニジャナクテ カレー」が、できた! #カレーキャラバン #サードシーズン #currycaravan
途中で雨がぱらつくことはあったが、大きなトラブルもなく「イモニジャナクテ カレー」ができあがった。里芋入りとはいえ、芋煮じゃなくて、カレーをつくっていたので(しかもカセットコンロで)、なんだかちょっと肩身がせまいような気分になった。終始、芋煮の「文化」に驚き、感心しながら過ごした。カレーキャラバンが大いに共感し、さらに極めるべき「ゆるさ」について考える機会になった。
とにかく楽しかった。この先も、器財を携えて旅を続けると思うが、このように「きちんとしたゆるさ」がある場所に出会うことができれば、ぼくたちは、いつも以上にいきいきと過ごすことができるはずだ。そのような「キャラバンフレンドリー」な場所は、この河川敷のほかにも、きっとたくさんあるにちがいない。あまりにも楽しすぎて、このあと、ぼくも亜維子さんも、しばらくのあいだは「芋煮ロス」に苛まれながら過ごした。🍲